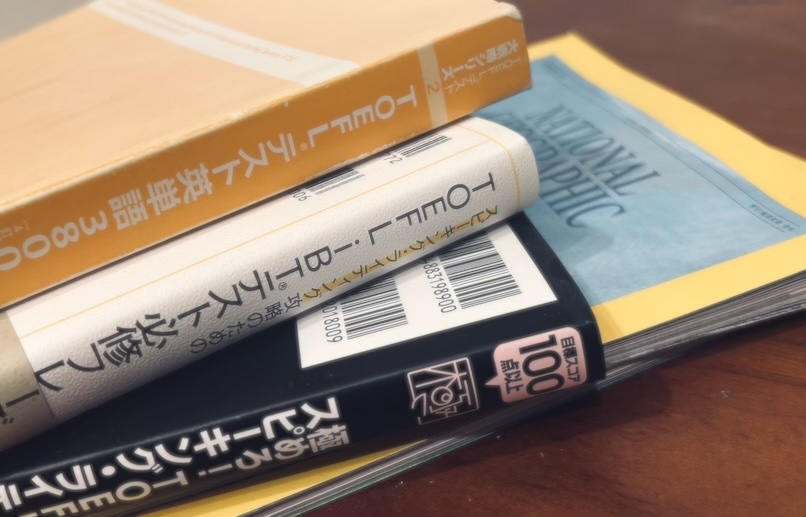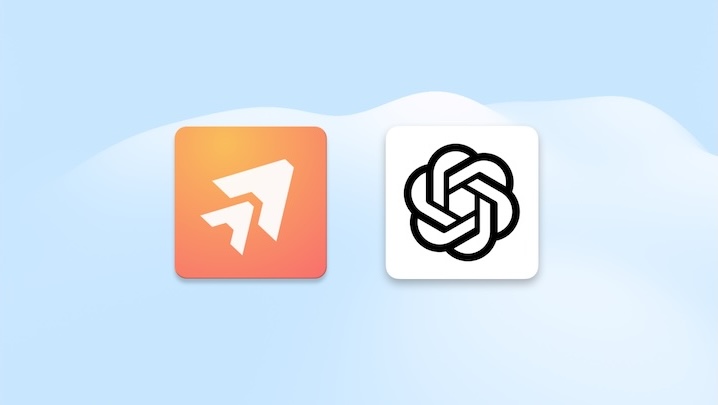TOEFL iBT 100点までの道のりと対策の記録

今回はTOEFL対策目指せ100点の回。日本人にとってTOEFL対策がアメリカ大学院準備の大部分を占めます。ベースの英語力次第ですが大抵1年弱かかると思います。
僕の場合は勉強開始を起点として1ヶ月後に初受験し79点。9ヶ月後8回目の受験で100点に到達しました。
この記事では80点弱から100点に上げるまでの対策について書きます。80点くらいだとCEFRでB1の上くらいです。実際自分も最初は英会話、リスニングは日常会話レベル、TOEIC(R&L)は800強だったと思います。
それくらいの方を対象に書いていきます。TOEFL対策が大変なのはよくわかります。対策中は藁にもすがる思いでいろんな記事を読みたくなります。少しでもこの記事が誰かの参考になればと思います。
廃課金で勝つ
まず身も蓋もないですが、金をかけます。受験料1回195ドル、高いですねえ(僕の時は245ドルで為替は155+円/ドルでした😇)。でも大学院進学はもっと高いです。10回受けても受験料は誤差です。腹括って課金します。
勉強継続してベースの実力を上げつつ、回数受けてラッキーパンチも狙いましょう。95点の実力で100点を狙う感じです。S(Speaking)とW(Writing)は数受けても実力相応にスコアが安定しますが、R(Reading)とL(Listening)は結構難易度ブレます。
勉強法
単語
界隈で有名なTOEFLテスト英単語3800で決まり。最初にザーッと全部読んでわからなかった単語を抽出し、Anki Appに入れます。あとはAnki Appで毎日チェックし、何周も何周もして頭に叩き込みます。
AnkiApp向けの単語カードを作る方法は別記事で紹介しています: ChatGPTを使ってAnkiAppの単語カードを作らせる【プロンプト付き】
中国TPO
TOEFL対策を語る上で避けて通れないのは中国TPO。TOEFL対策界隈でも有名です。中国TPOの問題セットは全てTOEFL公式のものなので、問題の品質は完全に本番相当です。
普通にアクセスすると会員登録を促されますが、直リンで行けばログインしなくても使えるのでリンク置いておきます↓
https://toefl.kmf.com/listen/ets/new-order/1/0
ただ中国の回線じゃないと使えないようになっていて、画面がボヤけます。有志が作ったChromeエクステンションを使えば使えるようになるので調べて入れてください。サイトアクセス後の使い方はいろんなサイトで扱ってますので、ここでは書きません。
中国TPOで問題を解きまくり、解いた問題の回答時間と正答率をスプレッドシートに記録しましょう。
Reading
ChinaTPOときまくる。時間も計って18分以内で解くようにします。正答率と回答時間のバランス感覚を養います。満点でも遅いと意味ないし、速く解いても間違ってたらやはりダメです。
1問といて答え合わせし解法を読み、読み解くのが難しかったセンテンスを理解し……とやると1問大体45分の勉強時間になります。毎日やると他の科目に手が回らないので2日に1回とかで良いと思います。
自分は90問解いた時点で解答時間16分で正答率92%くらい。解答見ても納得いかない問題もあるので満点を出し続けるのは難しいです。ただここまで仕上がった状態で本番で30点出せました。
Listening
これも中国TPOはある程度有効です。というのもTOEFLワールドがあります。例えば大学内の選挙や、チャリティイベントや寮の話など。
例えば「Johnson Hall」とか突然言われて、これが寮の名前であることは想像できないです。大学の寮の名前は人名+Hallみたいなのが多いので、知ってれば寮の話だと分かるのですが、知らないと何かコンサートホール的なものを想像してしまいます。
こんな風にTOEFLワールドの世界観に慣らすことは大事だと思います。慣れてくると教授の発言の意図を問う問題も、「あ、ここ出そうだな」と分かるようになります。
当然解き終わったら復習し、スクリプトも聞き取れなかった文を読み合わせます。シャドーイングも有効です。これらの復習も含め1日2問といても30分くらいは勉強時間必要です。
さらに中国TPOだけ解いててもベースのListening力はそれほど上がらないと思うので、もう少しスピードの速い別の音源でシャドーイングも続けました。
自分は130問くらい解き、L27点まで上げました。
Speaking
これも中国TPOで練習するのが効果的です。
1問1問解いていき、回答の録音を自分で聞き、滑らかに言えるようになるまで同じ問題を何回も繰り返しました。
ベースの英会話力はオンライン英会話で継続して鍛えていましたが、TOEFLはオンライン英会話で使う単語やシチュエーションと違うので、中国TPOも練習するといいです。TOEFLは描写的・説明的な回答を求められますから、オンライン英会話ではディスカッションに入る前にデイリーニュースの内容を要約するようにしてました。
Speakingは精神的にもキツいので色々な教材に手を出しましたが、劇的にスコアが上がる教材・サービスはないと思います。例えば参考書2冊買ったり、オンライン英会話はTOEFL向け教材がある「ベストティーチャー」もやりましたが特に有用だと感じたものはなかったです。勉強が辛いと他の勉強法や教材に目移りしてしまうかもしれませんが、効率いい方法は中国TPOを滑らかに言えるレベルまで何度も練習することだと思います。オンライン英会話で基礎体力を鍛えつつ、TOEFL特化の筋力は中国TPOで。
Speakingの辛いところは自己採点ができないので成長の実感が湧かないところです。ただ、本番の採点結果は実力相当で安定するイメージがあります。少しのスコアの向上も喜んでモチベーションに変えましょう。
自分は初回16でしたが、17,19,20と徐々に上げ、最後に22で総合100超えしました。
Writing
これもやはり中国TPOを解きます。英作文向けのフレーズを覚え、文章構造を意識し、最終的には22点で総合100点達成しました。多分失点はスペルミスと文法ミスが中心でこれはなかなか鍛えるのが難しかったです。
新形式のチャット形式の問題は中国TPOでは対応できませんが、基本的には旧形式の2問目と問われていることは同じで、あるテーマについて賛成か反対かとその論拠についてです。なので旧形式の2問目で回答時間と目標文字数を新形式基準に調整して練習すれば有効です。
スペルミスや文法ミスは校正ツールのGrammarlyで添削しました。
文章構造(特に2問目)
多くのTOEFL対策サイトは即使えるテンプレを載せてますが、僕は英語のEssay(小論文)の構造と書き方を知るのが結構大事だと思ったので書きます。
数をこなすとEssayの形式がわかってきます。EssayのパラグラフにはIntro, 複数のBody, Conclusionがあり、各Bodyパラグラフにはトピックセンテンスとサポートセンテンスから成るという、英作文のお約束の展開方法があります。これは後にGREのWritingやStatement of Purpose(SoP)等でも使う考え方です。
詳しい理屈・構造はもっとプロの人が紹介しているので探してみてください。
さらに、日本語のサポートセンテンスはトピックの背景や理屈の情報を付与することで説得力を持たせますが、アメリカではサポートセンテンスに具体例や実益/実害を上げることで説得性を与えることが多いです。
上の大阪大学の例が良いので拝借しますが、日本語だと下記のようにLUUPがどういうものか?に焦点を当てがちです。
- Topic: 京都市内では、LUUPとよばれる電動マイクロモビリティが広く普及している。
- Support1: LUUPとは、電動キックボード・電動自転車のシェアサービスのことである。
- Support2: スマホ一つ持っていれば、街中に設置された電動自転車に簡単に乗り降りすることができる。
- Conclusion: その利便性等が評価され、京都市と連携しながら更なる設置が進められている。
これがアメリカのサポートセンテンスであれば
- Support1: 利点は低いコストで、例えばXX、〇〇間の電車移動に比べ半分のコストで移動できる。
- Support2: さらに環境負荷も低く、ガソリン不要な上、1kmの移動に必要な電気料金はわずかxx円である。
といった感じで仕組みや原理に触れず具体的なメリットが焦点になります。これは文化的背景の違いだそうで、The Culture Mapという本に書かれていますが、アメリカでは実益主義的な展開方法が優れた説明と考えられるそうです。原作がアメリカのビジネス書などを読んでいると、具体的な人物とシーンで概念を説明していくパターンをよく目にするのはこのためです。
そして説得力があるか(Convincing)は採点基準にもあるのでアメリカの流儀で説得してやりましょう。僕はTOEFL対策中はこのことを知らなかったのですが、その後GREやSoPでEssayを書くうちにこのようなお約束を知ったので、この場でTOEFL対策中の人に伝えたいと思いました。
その他の勉強
流石にTOEFLだけやってると飽きるので、以下の練習も取り入れてました。
- National Geographic読む
- TOEFLっぽいのが多い。Webで読んでいたら結構面白くて紙の雑誌まで定期購読してしまった。
- オンライン英会話(Speakingの基礎トレーニング)
- シャドーイング(Listeningの基礎トレーニング)
- 実践
- ネイティブの友人と週1で深夜まで飲む
- 渋谷あたりで英語Onlyのミートアップに参加(Meetupで探せるよ)
- 言語交換アプリHello Talkでトークルームに入り浸る(ビール飲みながら)
飲み会で4時間くらい話すとオンライン英会話よりよっぽど鍛えられます。バーとか飲み屋はノイズも多いですし、深い話もできるし、酔って頭が回らなくても喋り続けるので無意識の英作文回路が出来上がります。
この辺りはそのうち記事書きます笑
100点の内訳
よくネットで「日本人はRLが得意だからそこで28点以上とり、SWは22点以上を狙って100点を出す」みたいな戦略を見ます。
僕もこれは正しいと思います。やってみて、日本人感覚ではRとLは割と点数が取れます。少なくとも無理ゲー感はありません。一方で、SWは義務教育で培ったベースの力も弱い上に、自己採点もできず、効率の良い伸ばし方がわかりません。
ただ悩ましいのは、SWも軽視はできない点です。100点目指す配分はRLがリードするんだが、勉強時間的にはSWもやはりちゃんと確保が必要です。
おわりに
ということで多くの日本人同様、僕も苦しんだTOEFL対策についての話でした。
別記事でTOEFLのオススメの受験方法としてHome Edition についても書いてますので、ご興味ある方はどうぞ: TOEFLはHome Editionがオススメ!メリットや注意点など
おそらく色んな方が多くの情報発信をされているので、目新しいものはなかったかもしれませんが、TOEFL対策を志すor長い戦いに疲れた誰かの参考になれば幸いです。
英語学習は色々とネタも多いので引き続き書いていきます。では!